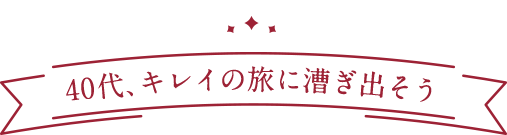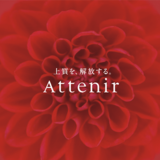「むくみ」はなぜ、どうして起こる?
■体内のバランスが崩れ「むくみ」が起こる

「むくみ」は、体内の水分が滞っている状態を言います。具体的には、細胞の内と外でやり取りされる物質を回収しきれず、バランスが崩れることで水分が滞って「むくみ」が起こったり、血液中の水分が外に漏れ出ることによって「むくみ」が起こったりします。
こうしてみると、バランスが悪いのは水分だけのように聞こえますが、そもそもこうした状況が起きるのが「体内のどこかのバランスが崩れている」サインとも言えます。
■東洋医学での「むくみ」も「水の滞り」
東洋医学でも、「むくみ」は「水の滞り」とされています。「水毒(すいどく)」、「痰湿(たんしつ)」、「水滞(すいたい)」などさまざまな呼ばれ方をしますが、いずれも「水が滞り、体の中でなにか悪さをしている」といった意味合いを持っています。
東洋医学では「気・血・水が過不足なくスムーズに巡っている」状態が最も健康とされます。しかし、ストレスや運動不足、同じ姿勢で長時間過ごすなどさまざまな原因で気の巡り・血の巡りが悪くなると、これらと関連の深い水の巡りも影響を受けて「むくみ」が起こります。
■水分の摂り過ぎ以外にも……さまざまな「むくみの原因」

「むくみ」は単純な理由だけではなく、人それぞれの体質や臓器の調子、ホルモンの影響など、さまざまな要因が絡み合って起こります。
人によって「朝むくみやすい」、「夕方むくみやすい」といった時間による特徴が出ることもありますし、よく言われる「水分の摂り過ぎ」はもちろん、一見逆の「塩分の摂り過ぎ」が影響することもあります。
■「むくみ」を放っておくとどうなる?
「むくみ」というと、腫れぼったい見た目や手足の違和感といった症状ばかりが気になって、その症状が収まれば「もう平気だ」と考えるかもしれません。
しかし「むくみ」は、東洋医学でいう「未病」のひとつ。病気というほどの状態にはまだなっていない、ちょっとした不調ではありますが、どこかで体内のバランスが崩れ始めているのです。ここはぜひ「放っておくと悪化して病気になりかねないよ」という身体からのサインだと考えて、未病のうちに体調を整えていきましょう。
大人世代と「むくみ」の関係
■生命を支えるエネルギー「腎精(じんせい)」のこと
東洋医学では生命を支えるエネルギーのことを「腎精(じんせい)」と呼びます。腎精はたとえるならロウソクのようなもので、人は生まれた瞬間から日々腎精を燃やしながら生きていき、尽きるとともに亡くなると考えられています。生まれ持った腎精の特性、いわゆるロウソクの長さは人によっても違いますが、では長いから必ず長生きできるかというと、そうでもないのです。

たとえば暴飲暴食が続く、ストレスが多い、睡眠不足などの生活習慣の乱れにより、ロウソクは長くても減り方がうんと早くなってしまう。逆にロウソクが短くても細々と燃やせる方は、比較的長生きするケースもあります。女性だと7の倍数、男性だと8の倍数の年齢で体が大きく変化すると言われ、この腎精の減り方も女性は28歳、男性は32歳をピークに下降していきます。
■40~50代は「腎」が弱くなることでむくみやすく

東洋医学では「五臓」という考えがあり、肝・心・脾・肺・腎(かん・しん・ひ・はい・じん)の5つを指します(西洋医学での臓器と全く同じ役割ではありません)。40~50代を迎えると、腎精を蓄えている「腎」(腎臓のことではなく、内分泌系、泌尿・生殖器系、免疫系、中枢神経系の一部)が弱くなってきます。それに伴い泌尿器のトラブル、生殖器のトラブル、ホルモン系の乱れが出はじめ、水分も大きく関わるところですから「むくみ」も出やすくなります。ちなみに「肺が弱ると上半身がむくみやすい」、「胃腸が弱ると手足や体全体がむくみやすい」、「腎が弱ると下半身や顔がむくみやすい」といった風に、弱っている臓器によってむくみやすい場所も変わってきたりします。
「むくみ」を解消し、むくみにくい体を作るには?
■睡眠をしっかりとる
睡眠は体を修復するためにも重要ですし、睡眠中には成長ホルモンも分泌されますから、腎を弱らせずに、元気にしてあげるにはとても重要です。
眠る時間ももちろんですが、質も意識する必要がありますので、以下記事もご参考にしてみてください。
■疲労やストレスを溜めない
過度な疲れやストレスは腎を傷める原因になります。とは言え、疲れることは一切しない、ストレスフリーに生きる……で通すことも難しいでしょうから、疲れたら早めに回復、ストレスを感じたらすぐ発散することを考えて「溜めすぎない」ようにしましょう。
KIREI Cruiseでは、心安らかに生きていくために重要な「自己肯定感」について、医師に取材した記事があります。
「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンを補うことができる食材もご紹介しています。
■体を冷やさない
また、東洋医学では体を冷やすことも、腎を傷める原因と考えられています。近年は夏もずっと冷房を使わざるを得ない気候になっているので、基本的に体の冷えている方が多いですから、冷やさないことも意識していきましょう。
身体を冷やさないために、日常から簡単に取り入れられる方法には以下のようなものがあります。
・方法1:補腎に良い食材や温かい食事を意識する

腎を元気にすることを「補腎(ほじん)」と言います。実は、補腎に良いとされる食材は黒豆、黒ごま、キクラゲなど「黒い食材」が多いのです。ほかにはクルミや栗、クコの実のように、芽が出る部分を食用する「種のもの」も、とてもエネルギーが多いので良いと考えられています。また現代栄養学でもスタミナ食材とされている豚肉や牡蠣、栄養価が高いブロッコリーやカリフラワーも腎を補う食材だと言われています。
体を温められる食事の摂り方も重要です。時間がない時は冷たいものをサッと食べて済ませたりしがちですが、朝、家にある野菜や肉でお味噌汁1杯作るだけでもいいですし、夜は野菜サラダを買う代わりにカット野菜で簡単なお鍋を作っても良いですし、ちょっとだけでも温かいものを食べるように心がけましょう。
・方法2:3つの『首』と、おなか・腰を冷やさない
体を冷やさないために温めるポイントとして、「3つの『首』」が重要です。頭が載っている「首」と「手首」、そして体を支えている「足首」ですが、いずれも大きい血管が通っている場所なので、ここが冷えてしまうと体全体が冷えやすくなってしまいます。露出しやすい場所ですが、マフラーや手袋、靴下で守ってあげましょう。
また、女性はおなかや太もも、おしりが冷えてしまう方も多いですが、まさに「腎」の周辺になるので、ここも冷やさないように意識したいですね。着るもので守るのもそうですし、お風呂にちゃんと浸かって温まるといったことも大事です。
もし、それでも「むくみ」が出てしまったら……?
■シンプル・イズ・ベスト!「横になって足を高く」する

足に「むくみ」が出た場合、一番手っ取り早い対策は「横になって足を心臓より高くする」ことかもしれません。そんな単純な方法で……と感じるかもしれませんが、足は心臓から遠いですし、立ったりしていると重力もかかるので、降りてきた血液や水分を押し上げて戻さないといけなく、意外と大変です。
歩いたりして足をよく動かしていると、筋肉がポンプのように血管やリンパ管を圧すので戻しやすいですが、立ちっぱなし、座りっぱなしとなるとどうしてもむくみやすくなってしまいます。そこで、足を高くして自然に「戻る流れ」を作ってあげると、「むくみ」も解消しやすくなるのです。
■横になれない時は「むくんでいる部分を刺激」してみる
家の中ならすぐ横になれても、職場やお出かけ先ではそうもいかないですよね。そういう時は、むくんでいる部分を揉んだりして刺激してみるのも良いと思います。むくみ対策のツボもご紹介するので、図を参考にして押してみてくださいね。
腎兪(じんゆ)、命門(めいもん)

腎兪:へその高さで腰に手を置くと、自然に親指が届く位置にあります。
命門:へそのちょうど後ろ側、背骨の上です。
いずれも、むくみのほかに、疲労回復、腰痛などにも効果が期待できます。
関元(かんげん)

へそから指4本分ほど下の位置にあります。
むくみのほかに冷え、疲労回復などにも効果が期待できます。
三陰交(さんいんこう)

手の指を4本そろえて、内くるぶしの一番高いところに小指を置き、人さし指が当たっている場所。すねの骨の後ろ側のふちにあります。
むくみのほかに冷え、婦人科系の不調などにも効果が期待できます。
豊隆(ほうりゅう)

膝の皿と足首を結ぶすね中央の高さで、すねを横から見て横幅のほぼ真ん中に位置しています。
むくみのほかに胃腸の不調などにも効果が期待できます。
正しいやり方やツボの位置などを気にし過ぎるよりは、気軽にトライしてみてください。「このあたりかな?」と、自分で気持ちの良いところを探ってみても構わないです。普段、自分の体を意識して触る機会のない方も結構多いと思いますが、日常的に触っていることでわかってくることもあるので、どんどん自分の体を触るようにしてみましょう。
■単純に「手足、体を動かす」だけでも!
結局、滞っているからむくんでしまうわけなので、実は手足、体を動かすだけでスッキリしてくる可能性も十分あります。同じ姿勢をとることが続いたりするとむくみやすくなるので、たとえば1時間に1回は屈伸運動をしてみる。席を立てないならこっそり先ほどのツボを押したり、足を揉んでみたりするだけでも良いと思います。
漢方にもトライしてみよう
■当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
血が不足している方や血の巡りが悪い方、婦人科系の不調がある方に使われることが多いです。血の巡りの悪さが「むくみ」につながっている人、たとえば1日中デスクワークをしている方や、「むくみ」とあわせて婦人科系の不調もあるような方にはおすすめです。
■五苓散(ごれいさん)
まさに「体の水はけを良くする」漢方ですので、水分の摂り過ぎに心当たりがあったり、お酒をよく飲んだりしていて「むくみ」が出やすい方にはおすすめです。
■防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
消化吸収を助けながら、「体の水はけを良くする」漢方です。疲れやすくよく汗をかく「水太り」タイプの方におすすめです。
漢方薬の服用にあたっては、もちろん専門家に相談するのが一番ではあります。ただ、ここでご紹介した3種類の漢方薬は、どなたが飲んでも悪い影響が現れるようなことは考えにくいかと思いますので、まずは身近なドラッグストアなどで購入して試してみるのも良いかもしれません。
未病は「体からのサイン」という話をしましたが、決して「まだ大丈夫」とは解釈しないでほしいです。早めに体の声を聞いて改善したほうが、後々辛い治療で大変な思いをしたりするよりもラクなはずだからです。だから、まだ大丈夫、ではなく「未病のうちに」と言われたつもりで、自ら体をケアしていきましょう。ご紹介した対策方法も、まずはやってみてご自身に合うものを選択するというのも良いと思います。
人生100年時代、家電や車は買い替えられても、体は変わらず1つだけです。「この体で100年生きていくのだから」と考えて、大事に使ってあげてくださいね。
- ●監修者
田中友也(たなかともや) -

鍼灸師、国際中医専門員、国際中医薬膳管理師、登録販売者資格保持。関西学院大学法学部卒業後、イスクラ中医薬研修塾にて中医学の基礎を学び、北京中医薬大学、上海中医薬大学などで研修。現在、兵庫県にあるCoCo美漢方(ここびかんぽう)で日々、健康相談にのる傍ら、鍼灸師として施術も行う。SNSやコラム上でも親しみやすいトーンで、漢方や中医学など東洋医学の普及に努めている。またオンラインセミナーなども積極的に開催している。