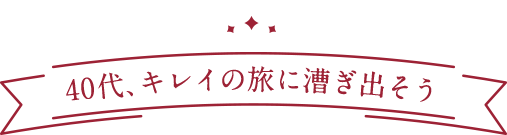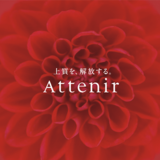神社とお寺、両方に参拝してもいいの?

神社は神道の信仰に基づいて、神様(御神体)を祀っています。一方、お寺は仏教の信仰に基づいて、仏様(仏像)を祀っています。
とはいえ、神道と仏教がはっきりと区別されたのは明治時代からで、それまでは人々の暮らしの中でおおらかに混ざり合っていました(神仏習合)。神社にあるはずの鳥居がお寺にあったり、神社とお寺が隣接していたりするのは、神仏習合の名残と言えます。
もともと混ざり合っていた信仰ですから、もちろん両方参拝しても問題ありません。たとえば初詣をはしごしたとしても、初詣は神社で先祖供養はお寺であっても構わないのです。
神社・お寺の参拝ルートを確認!
神社・お寺の敷地に入ってから、出るまでのルートは以下のとおりです。玄関にあたる場所や拝む場所の呼び方が異なります。
ちなみに、お守りや御朱印を授かったり、おみくじをひいたりするのは、神様や仏様にご挨拶をしてから行うのがマナーですから、拝殿や本堂を拝んだ後にしましょう。次からはそれぞれの作法を解説します。

■神社・寺共通:手水のお作法
手水(てみず、ちょうず)は身を清める行為なので、神様・仏様へ参拝する「前」に行います。作法は神社・お寺共通です。ポイントは「ひしゃく一杯の水ですべての手順を済ませる」こと。事前にハンカチを出しておいてカバンなどにひっかけておき、すぐに使えるようにしておくと、慌てないのでおすすめです。

1:手水舎の前に立ちます(ハンカチを用意)。右手でひしゃくを持ってたっぷりと水をくみ、1/3くらいの水を使って左手を清めます。
2:水をこぼさないように気をつけながら左手にひしゃくを持ち替え、同じく1/3くらいの水で右手も清めます。
3:再び右手にひしゃくを持ち替え、残った水の半分ほどを左手で受け、その水で口をすすぎます。
4:左手を洗い、最後に残った水で使ったひしゃくを清めます。柄に水が伝わるようにひしゃくをそっと立て、手で触れた部分まで流して完了です。
ひしゃくがなく水道のように流れる水を使用するタイプの場合は、軽く手洗いするように両手を清め、両手に水をためて口をすすぎ、最後に再び両手を清めればOKです。
神社参拝のお作法
一般的な神社は、後述するように「二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)」が作法です。神社にお参りする際の作法を、順番に見ていきましょう。
■鳥居をくぐる〜手水舎

鳥居の先は神様の住まう神域です。くぐる前に服の乱れを整えて、帽子は脱いでおきましょう。軽く一礼(会釈程度)して鳥居をくぐります。参道の中央は神様の通り道ですから、左右の端を歩いて進みます。
「神社・寺共通:手水のお作法」を参考に身を清めたら、拝殿に向かいましょう。
■拝殿で参拝「二拝二拍手一拝」

賽銭箱のすぐ手前が神様をお参りするための拝殿です。混同されがちですが、神様がいらっしゃる本殿とは区別されています。
1:拝殿についたら軽く礼(会釈)をし、お賽銭を入れます。
2:鈴がある場合は両手で鈴緒(すずお・鈴を鳴らすための紐)を持って鳴らします。
3:いよいよ参拝です。まず深いお辞儀を2回、そして拍手(かしわで)を2回、最後に再び深いお辞儀を1回行います。これを「二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)」と言い、ひと続きの流れとして一気に行います。その際、合掌はしません。
4:その後で頭を軽く下げ、祈願します。混雑時には、二拝二拍手一拝を終えたら脇によけ、邪魔にならない場所まで行って拝むのも良いです。
二拝二拍手一拝は一般的な神社の作法です。出雲大社では4回手を打ち鳴らす「二礼四拍手一礼」が正式であるなど、神社によって違う場合があります。心配な時は事前にお参りする神社の公式ホームページでチェックしておくと安心です。
■鳥居をくぐって出る

参拝を終えたら、お守りや御朱印を授かったり、景色を楽しんだり、思い思いの時間を過ごしましょう。帰る際は再び参道の端側を通り、鳥居を出る前に社殿に向き直って会釈をして出ます。
お寺参拝のお作法
続いて、お寺を参拝する際の作法をみていきましょう。お寺では音を立てずにお参りするのが基本なので、拍手は打ちません。
■山門をくぐる〜手水舎

山門(さんもん)はお寺の門のことで、三門とも言い、俗世間と仏道世界の境界の役目をしています。門前にカッと目を見開いた阿吽像(あうんぞう)や一対の狛犬がいるのは、悪いものが内に入ってこないようにするためです。
服の乱れを整えて脱帽し、軽く一礼(会釈程度)をしてから山門をくぐります。その際、山門の敷居を踏まないようにまたいで通りましょう。また、参道の中央は仏様の通り道ですから、左右の端側を歩いて進みます。
「神社・寺共通:手水のお作法」を参考に身を清めたら、拝殿に向かいます。
■本堂で参拝

いよいよ参拝です。会釈をしてお賽銭を入れ、鰐口(わにぐち・鼓状の鐘のような仏具)がある場合は、鉦の緒(しょうのお・鳴らすための紐)を両手で持って鳴らします。再度礼をし、胸の前で合掌、手を合わせたまま祈願します。最後にもう一礼して参拝を終えます。拍手は打ちません。
合掌とは左右の手を合わせることで、仏の世界と人とがひとつになるように(=成仏)という祈りのかたち。したがって、神社には合掌という所作はありません。
■山門をくぐって出る
参拝を終えたら、神社と同様に思い思いの時間を過ごしましょう。帰る際は再び参道の端側を通り、山門を出る前に本堂に向き直って会釈をして出ます。
お守りって複数持っても大丈夫?

結論から言えば、お守りは複数持っていても問題ありません。「神様と仏様がケンカする」という風説がありますが、そんなことはないので安心してください。ただし、失礼のないよう、お守りは丁寧に扱いましょう。大切に身につけるか、目線に入る高さでかつ清潔な場所に置くなど、敬う気持ちを表すことが大切です。
また、お守りは1年が有効期限という説もありますが、思い出のあるお守りや、叶うまで持っていると願掛けしたお守りはずっと持っていても大丈夫です。もちろん、1年無事に過ごせたことの感謝として、また、引っ越しや受験などの節目に、お守りを新調するのもOKです。

お守りを処分する際には、授かった神社・お寺に自ら出向いて納めるのが基本です。難しい場合は近所の神社・お寺の「古神札納め所(ない場合は社務所のスタッフなどに相談)」に納めたり、近ごろではお焚き上げの郵送サービスなどもあります。
神社やお寺をお参りするのに大切なのは、敬う気持ちです。お作法はその気持ちを伝えやすくする所作と言えます。心をこめてお参りし、「叶うようにがんばるので、見守っていてください」と願えば、清々しく前向きになれるはず。神様・仏様を味方につけて、たくさんの良いことがありますように♪